-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
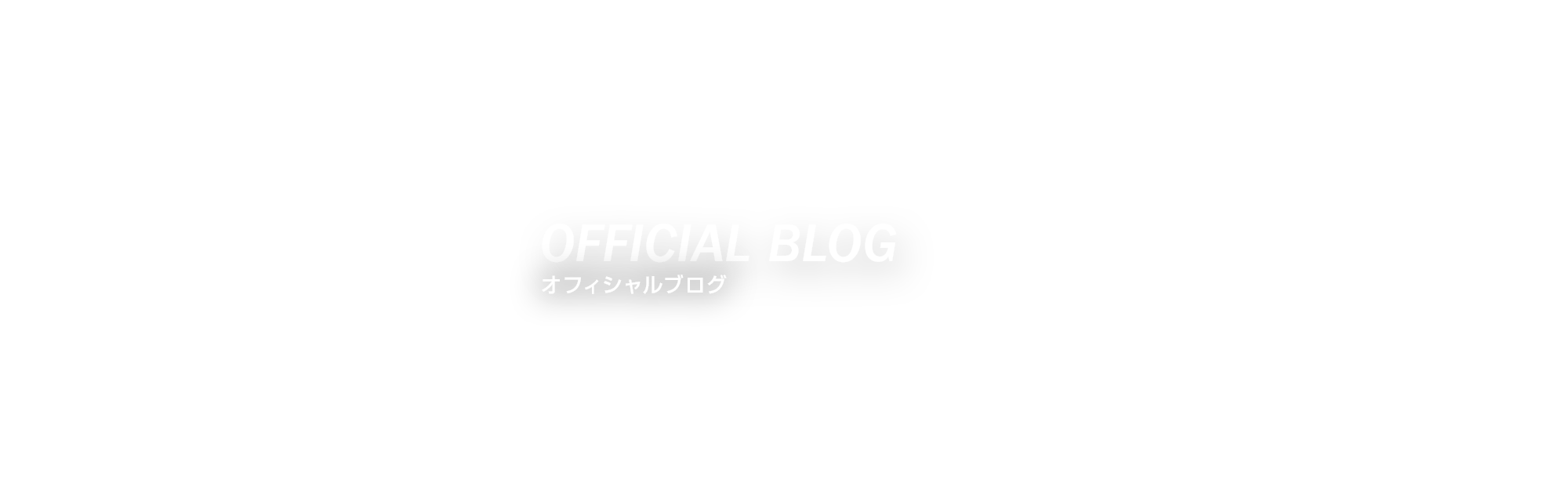
皆さんこんにちは!
龍輝物流、更新担当の中西です。
目次
今回は、物流の現場で欠かせない作業「デバンニング(Devanning)」について、その歴史的な背景と進化の過程をたっぷりと解説していきます。
普段、何気なく使っている「コンテナ」。このコンテナから貨物を取り出す作業、すなわちデバンニングは、実は現代の国際物流を支える重要工程のひとつです。では、このデバンニングという作業は、いつからどのように始まり、どのように進化してきたのでしょうか?
デバンニングの起源をたどると、19世紀末〜20世紀初頭の海運時代に行われていた**港湾の「バラ積み荷役」**にたどり着きます。
船が入港すると、荷役労働者(ドックワーカー)が手作業で積み荷を一つ一つ荷下ろし
荷の形や重さ、大きさがバラバラで、破損・盗難も多発
荷下ろしに数日〜1週間以上かかることも珍しくありませんでした
このような手間と時間のかかる荷役を劇的に変えたのが、コンテナの登場です。
1956年、アメリカの実業家マルコム・マクリーンによって、**貨物を専用の鉄製箱(コンテナ)に詰めたまま輸送する「コンテナ輸送」**が考案されました。
これにより、
輸送中の荷崩れ・盗難が激減
船→トラック→鉄道と、貨物が箱ごとスムーズに移動可能に
港での積み下ろし時間が大幅に短縮
このとき、コンテナから荷物を取り出す作業が必要となり、デバンニング作業が誕生したのです。
日本では1960年代、東京港や神戸港においてコンテナ船の試験運用が始まり、1971年には日本初の本格的コンテナ埠頭が東京・大井に完成。
以降、輸出入貨物の大半がコンテナ化されるようになり、それに伴ってデバンニング専門の事業者や作業チームも生まれました。
初期は港湾労働者が手作業で対応
現在では、物流倉庫や流通センターでの荷下ろし専門スタッフが担うことが主流に
デバンニングのスピードと正確性が、物流の流れ全体に影響を与える重要工程に
21世紀に入り、国際物流はさらに複雑化し、デバンニング対象の貨物も多様化しています。
家電・アパレル・雑貨・食品・資材など、多岐にわたる商材
冷蔵コンテナ・パレット積み・バラ積み・大型品など、作業方法も多様
作業現場ではフォークリフトやハンドリフト、バーコード検品システムの導入が進む
さらに、人手不足への対応としてAI・ロボット化の導入実験も行われており、デバンニングの未来は今まさに進化の真っ只中にあります。
表舞台には出ないけれど、物流のスタート地点を支える最前線にあるのがデバンニングという仕事。
「コンテナの中身を的確に、迅速に、安全に下ろす」――その積み重ねが、スムーズな流通を実現しているのです。
次回は、そんなデバンニングの現場で守られている“鉄則”について詳しくご紹介します!
次回もお楽しみに!
龍輝物流では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()